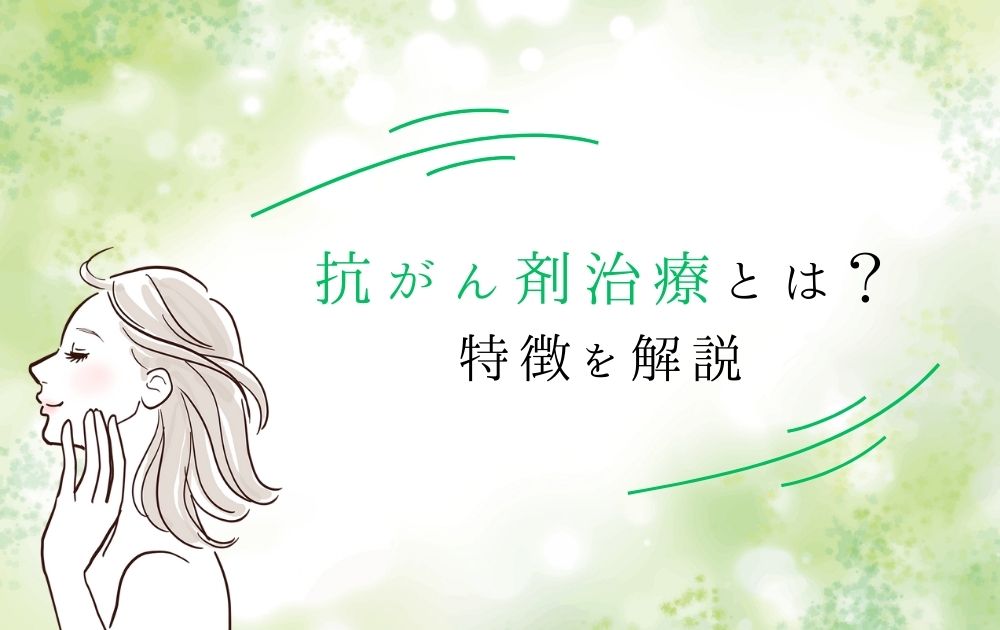抗がん剤治療は、がんの治療をする上で有効な治療法の一つです。
しかし、実際に抗がん剤治療がどのような治療なのかを良く知らない人が多いのではないでしょうか。
今回は抗がん剤治療がどのような治療なのか解説していきます。
1. 抗がん剤治療の特徴
1-1. 抗がん剤って何?
抗がん剤とは、がん細胞の増殖を抑えたり、成長を遅らせたりすることで、がんの再発・転移を予防するために使用される薬剤のことです。
薬剤には主に、錠剤やカプセル剤などの口から投与する「内服薬」と、血管に直接薬剤を投与する「点滴剤・注射剤」があります。
がんへの局所的な治療法である“手術”や“放射線治療”に対して、抗がん剤はより広い範囲に治療の効果が及ぶことが期待できます。
このため、がんの転移の可能性があるときや、手術後の再発・転移を予防するとき、血液・リンパ系の広い範囲のがんに治療を行う必要があるときに使用される場合が多くなります。 (注1)
1-2. 抗がん剤でがん細胞の増殖を抑える
抗がん剤は、作用の仕方の違いで大きく3つの種類に分けることができます。
(1)化学療法
がん細胞がDNAやタンパク質などを合成する過程を化学物質によって阻害することで、がん細胞の成長や増殖を抑える薬剤です。
少なからず正常な細胞にも影響を与えてしまうため、副作用が起こりやすくなります。
(2)分子標的薬
がん細胞だけが持つ分子の特徴や、がん細胞の中の増殖や転移に関係している遺伝子だけを標的にした新しいタイプの薬剤です。
がん細胞以外の正常な細胞には作用しにくいため、従来の抗がん剤よりも副作用は少なくなります。
(3)ホルモン療法(内分泌療法)
がん細胞の増殖にかかわる体内のホルモンを調節することで、がん細胞が増えるのを抑える薬剤です。
ホルモンの分泌を抑制したり、ホルモンが受容体と結合するのを阻害したりする作用があります。
一部のホルモン依存性の乳がんや前立腺がんに用いられます。
(注2)(注3)
2. 抗がん剤の副作用とは?

抗がん剤は、がん細胞だけではなく正常な細胞にもダメージを与えるため、治療を進めるにあたって副作用が起きることがあります。特に細胞の分裂や増殖が活発に行われる皮膚や毛根、腸管、骨髄で起こりやすいと言われています。(注1)(注4)(注5)
2-1. 発現する時期
治療当日
アレルギー反応、吐き気、発熱、血管痛
1週間以内
倦怠感、食欲不振、吐き気、下痢、便秘
1~2週間後
食欲不振、口内炎、下痢、便秘
3~4週間後
脱毛、骨髄抑制(白血球や血小板の減少、貧血)、膀胱炎、肝障害、腎障害
2-2. 副作用で起こりやすい症状
吐き気
吐き気は、抗がん剤が消化管の粘膜や脳の神経を刺激することで起こると考えられていますが、治療に対する不安などの心理的な要因も関係しています。
ほとんどの場合は、抗がん剤と一緒に吐き気止めが処方されますので、指示通りに服用しましょう。
脱毛
脱毛は、毛の根元にある毛母細胞が抗がん剤によってダメージを受けるために起こります。
髪の毛だけでなく、まゆ毛やまつ毛、体毛も抜け、皮膚に痛み・かゆみを感じる場合もあります。
脱毛が起こる時期をあらかじめ予想しておき、医療用のかつら(ウィッグ)や帽子、がん医療アートメイクなどを取り入れることで前向きに過ごすことができます。
そのほか紫外線や乾燥、摩擦による刺激にも気を付けることも大切です。
がん医療アートメイクとはの記事へリンク
貧血
貧血は、骨髄の中にある、血液を作る造血幹細胞が障害され、赤血球が減少したり、消化管などから出血したりすることで起こります。血液検査をするまで自覚症状がない場合もありますが、倦怠感、疲れやすさ、めまい、息切れなどの症状が現れる場合もあります。
感染症
抗がん剤の影響で白血球が減少すると、細菌やウイルスに対してからだの抵抗力が弱くなり、感染症にかかりやすくなります。
38℃以上の発熱やのどの痛み、膀胱炎、下痢、口内炎などの症状があれば感染症を疑い、医師に相談しましょう。
入浴や濡れタオルで体を清潔に保ち、外出時はマスクを着用、帰宅後は手洗い・うがいを徹底して予防しましょう。
なお、同じ抗がん剤を使用しても発現する副作用の種類や程度は人によってさまざまです。
気になる症状があれば担当医にすぐに相談し、副作用とうまく付き合いながら治療を進めていくことが大切です。
(注1)
3. 抗がん剤治療の方法

抗がん剤を投与する方法は複数あり、がんの種類や広がり方、病期(ステージ)、併用する治療法、患者さんの病状などを考慮して決定されます。
具体的には、以下のような方法があります。
- 飲み薬:錠剤やカプセル剤で口から服用する
- 点滴や静脈注射:血管の静脈から直接投与する
- 動脈注射:特定の臓器に流れる動脈にカテーテルを置き、薬を投与することで、血液の流れに乗ってその臓器に集中的に投与する
- 腹腔(お腹の中)内、胸腔(肺の周りの空間)内、脳脊髄液(脳や脊髄の中にある液体)へ直接注入する
飲み薬以外の抗がん剤は、副作用の観点から毎日投与することはなく、投与後に数週間程度の休薬期間が設けられます。
この投与期間と休薬期間を含めた1セットを「1クール」「1コース」と呼び、同じサイクルで数回繰り返して行われます。
(注1)
医師と相談しながら自分にあった治療法の選択を
抗がん剤治療と聞くと不安に感じる方がほとんどだと思います。
まずは、自分の受ける治療法がどのようなものか、担当の医師からしっかり説明を聞きましょう。起こりうる副作用やその対処法をあらかじめ把握しておくことで、不安を軽減できます。
治療は長期間に渡ることが多いため、担当医と相談しながらご自身にあった治療法や対処法を選択していきましょう。
【参考文献】
(注1)国立研究開発法人国立がん研究センターがん情報サービス.薬物療法(抗がん剤治療)のことを知る”.閲覧日2022年12月6日
https://ganjoho.jp/public/qa_links/book/public/pdf/31_139-149.pdf
(注2)名古屋大学医学部附属病院.“抗がん剤とは” 閲覧日 2022年12月6日 https://www.med.nagoya-u.ac.jp/surgery2/clinical/digestive/anti/about/
(注3)浦部晶夫(2020)今日の治療薬2020,南江堂,第42版
(注4)独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター.“抗がん剤の主な副作用と対処法”. 閲覧日 2022年12月6日
https://kobe.hosp.go.jp/cancer-medical/faq/qakouganzai.html
(注5)国立研究開発法人 国立がん研究センター 東病院.“抗がん剤治療中の症状に関するQ&A”.閲覧日2022年12月6日
https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/division/pharmacy/kouganzai/index.html