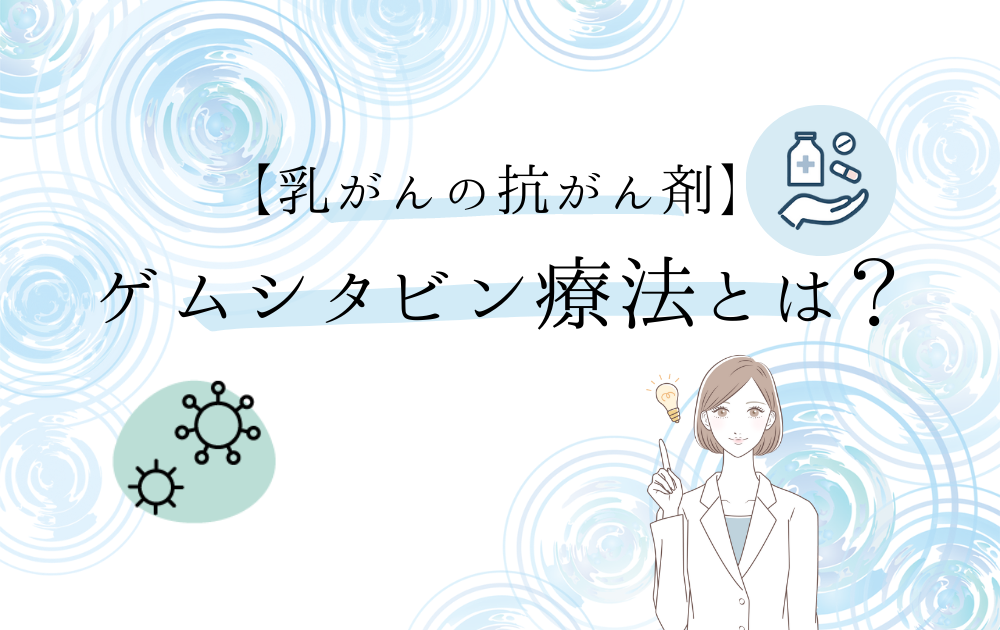ゲムシタビン療法(別名:ジェムザール)は、乳がん治療の薬として良く使われる抗がん剤治療の一つです。
手術ができない乳がんや、再発した乳がんの治療で使用する抗がん剤です。
この治療は点滴での治療になりますが、吐き気や骨髄抑制などをはじめとする副作用が出ると言われています。
本記事では、ゲムシタビン療法の一般的な治療法や投与方法、また、どのような副作用が起こりうるのかを、副作用の対処法などを含めて解説します。
1.ゲムシタビンの概要
ゲムシタビンは、がん治療の化学療法で用いられる薬剤で、点滴で行う治療薬です。
代謝拮抗薬の中において「ピリミジン拮抗薬」に分類される抗がん剤の一つとなります。
ゲムシタビンは入院して投与することもあれば、外来で投与することもできる治療です。
ただし、投与後は副作用が現れることがあるため、外来での投与には注意が必要です。
▼参考資料はこちら
2.ゲムシタビンとは?
ゲムシタビンは、乳がんや卵巣がんの進行を抑えるための全身治療としてよく使われる抗がん剤治療の一つです。
以下では、その特徴や体内での働き方、どのような効果が期待できるのかを解説します。
2-1.ゲムシタビンの特徴
ゲムシタビンは、手術ができない乳がんや再発した乳がんの治療で使用する抗がん剤です。
乳がんのほかに、化学療法後に悪化した卵巣がんなどにも効果があると言われています。
ゲムシタビンは、がん細胞の増殖に必要な物質とよく似た構造をしているため、がん細胞の中に取り込まれて効果を発揮する特徴があります。
2‐2.ゲムシタビンの体内での働き方
がん細胞は、細胞分裂を繰り返すことで細胞が増殖していきます。
そのがんの細胞分裂を抑制したり、成長を遅らせたりすることが抗がん剤治療の役目です。
ゲムシタビンは、がん細胞のDNAに入り込み、細胞分裂に必要なDNAの合成を阻害してがん細胞を死滅させ、がん細胞の分裂や増殖を抑える役割を果たします。
3.治療における使用法と投与量
ゲムシタビンでの治療は点滴で行います。
以下では使用法や投与量、周期について解説します。
実際の治療の進め方は医師の判断により患者さんによってそれぞれ異なりますが、一般的な使用方法と量を理解しておきましょう。
3‐1.ゲムシタビンの一般的な使用法
ゲムシタビンの投与は、一般的に4週間を一区切りとして、週1回の投与を3週間続け、4週目は休みとなるサイクルです。
スケジュールや投与量は、患者さんの体調次第で医師の判断により変化することがあります。
点滴時間は約45分程度となっており、内容はゲムシタビン注を30分、生理食塩液を15分です。
また、ゲムシタビン投与前に吐き気止めの点滴をする場合は、追加で約15分点滴時間が長くなります。
3‐2.ゲムシタビンの投与量と周期
ゲムシタビンの投与量は、患者さんの年齢や症状、体表面積を元に決められます。
また、患者さんに副作用が現れてからは、副作用の程度も見ながら医師が投与量を決定するので、患者さん全員が同じ投与量ではありません。
周期についても、患者さんの状態や体調によって変化します。
▼参考資料はこちら
4.ゲムシタビンの副作用と対策
ゲムシタビン療法は、ゲムシタビン注を体内に投与する全身的な治療です。
そのため、体内にあるがん細胞以外の正常な細胞にも作用してしまい、副作用が現れることがあります。
以下では、主な副作用とその対策について解説します。
副作用の種類や予防法、緩和策も知っておきましょう。
4‐1.主な副作用
副作用には、吐き気や下痢などといった自覚症状があるものと、骨髄抑制などの自覚症状がないものに分けられます。
主な副作用には、以下のような症状があげられます。
| 消化器症状 | 食欲不振・吐き気・嘔吐・下痢 |
| 骨髄抑制 | 白血球の減少・赤血球の減少・血小板の減少 |
| その他の症状 | 発疹・発熱・疲労感・口内炎・便秘・肝機能低下・腎機能低下 |
| その他重大な副作用 | 間質性肺炎・アナフィラキシー症状など |
4‐2.消化器症状
食欲不振・吐き気・嘔吐・下痢といった消化器症状は、点滴直後から1週間以内に現れることが多く、長く続くと脱水となり悪化してしまう危険性があります。
対策としては以下があげられます。
- 食欲がないときは無理して食べない
- 消化にいいものを食べる
- さっぱりしたものを食べる
- 熱いものはにおいが強いので冷ましてから食べる
- においで不快に感じるものは近くにおかない
- 口の中を清潔にする
上記の方法を行うことで、症状の緩和が期待できます。
4‐3.骨髄抑制
骨髄抑制は、ゲムシタビンの代表的な副作用の一つです。
骨髄の働きが低下する状態のことで、症状の自覚がないため、検査を受けなければ気付かない副作用となります。
一般的に点滴から1週間前後で症状が現れるといわれています。主な症状としては以下のとおりです。
| 白血球の減少 | 体の抵抗力が低下するため、感染症にかかりやすくなる |
| 赤血球の減少 | めまいや立ちくらみ、動機などの症状が出て貧血状態になりやすくなる |
| 血小板の減少 | 出血しやすくなる |
対策としては以下があげられます。
- 手洗い、うがいをこまめにして風邪にうつらないようにする
- 体に傷をつけない
- 安静にして体を休ませる
- 口の中を傷つけないようにやわらかいブラシを使う
上記のような対策を早めに心掛けておくことが重要です。
4‐4.疲労感
抗がん剤を使用すると疲労感が出ることがあり、一般的に点滴当日から2~3日続くといわれています。
もともと疲れやすい人の場合、より疲労感を感じることがあります。
- 体を冷やさないようにし、十分に休む
- 睡眠をとる
上記の対策法を心掛け、疲れたと感じたらしっかり体を休ませるようにしましょう。
4‐5.口内炎
ゲムシタビン治療によって、口内炎が出来やすくなります。
口内炎が出来ると食べ物が染みたり歯茎が腫れたりするなどの症状が出ます。
口内炎は食事がしづらくなるほか、感染症の原因になるのでしっかり対策しましょう。
- うがいをこまめにする
- 歯ブラシはやわらかいものを使う
- 熱い食べ物は避け、やわらかいものを食べる
できるだけ口の中を傷つけないように心掛けることが重要です。
治療中でも安心した生活を送ろう
今回は、ゲムシタビンの使用方法、副作用について紹介しました。
ゲムシタビンは、手術ができない乳がんや再発した乳がんの治療で使用する抗がん剤です。
点滴での全身治療となるゲムシタビン療法は、がん細胞のDNAに入り込み、細胞分裂に必要なDNAの合成を阻害してがん細胞を死滅させ、がん細胞の分裂や増殖を抑える役割を果たします。
一方で、抗がん剤ならではの副作用が現れてしまうことも事実です。
副作用の予防や対策をして、できるだけ症状が緩和するよう心掛けましょう。
抗がん剤での治療は、効果の高さと副作用のバランスを見ながら行います。
痛みや違和感があればすぐに医師に相談し、治療中でもできるだけ安心した生活が送れるようにしましょう。