がんになると、病気や治療だけでなくお金の心配もあるでしょう。
がんの治療には様々な方法があり、治療や病状によっては長期にわたる治療になることもあります。
そんながん治療の費用を抑えることはできるのでしょうか。
今回は治療の支払いに使える公的医療保険制度を解説します。
公的医療保険制度とは
公的医療制度には、国民健康保険や社会保険が該当します。
がん治療を受ける際に、働いている方であれば、国民健康保険や会社を通して加入している健康保険を利用し、3割の費用負担で検査や治療を受けることができます。
また、高齢者になると高齢者医療制度という形で、個々の収入に応じた負担で診察や治療を受けることができるように、国民皆保険制度で整備されている点が特徴です。
例えば、診察、入院、薬物治療など、公的医療保険の対象となる医療費用が合計200万円かかる場合でも、3分の1の金額である65万円ほどで、がん治療を受けることが可能と考えることができるでしょう。
しかし、国に認可されていない先進治療にあたる薬剤や、治療法を利用してがん治療を行いたい場合には、公的医療保険の対象にはなりません。
公的医療保険の対象になるのは、国が認めた治療や薬剤です。
そのため、もしもに備えたい際は、民間の生命保険会社の医療保険も併せて検討しましょう。
がんの治療に使える公的医療保険制度

がん治療を受ける際には、公的医療保険の対象となる診察や治療があるということは理解できた方も多いでしょう。
それでは具体的にどのような制度が用意されているのか、種類ごとに解説します。
高額療養費制度
高額療養費制度は、公的医療保険の対象になる医療費のうち、月の1日~末日までに医療機関や薬局の窓口へ支払った金額が一定金額を超えた場合に、超えた金額分が被保険者に戻ってくる制度です。
一定金額の基準は年齢や所得に応じて決められており、年齢は70歳を基準に大きく2つに分かれています。
所得に関しては370万円未満から1,160万円以上まで、細かく所得ごとに上限が定められているので、自分の所得はどのくらいの金額が1ヶ月の医療費上限と定められているのか、確認しましょう。
もしも、基準金額以上、1ヶ月で医療費がかかってしまった場合は、国民健康保険であれば市町村、会社の健康保険であれば、健康保険組合などに、相談することで払い戻しを受けることができます。
また、事前に1ヶ月の医療費が基準額を超えそうだと分かっている場合は、事前に市町村、健康保険組合などへ相談しましょう。
限度額適用認定証を発行してもらうことにより、窓口での支払いは決められた限度額までの支払いになります。
ただし、入院中の食事負担や差額ベッド代は含まれません。
公的医療制度
日本に住むすべての国民は、国民健康保険や会社を通じた健康保険、後期高齢者医療保険のいずれかに加入することが義務付けられている国民皆保険制度があります。
70歳未満であれば、実際にかかった医療費の3割で治療や診察を受けられるので、必要以上に負担がかかることを抑えてくれる制度です。
残りの7割は国が負担してくれるため、病院などの窓口では基本的に3割負担となります。
また、公的医療保険は加入している団体により、受けられるサービスが変わるため、不明な点がある時にはかならず確認しましょう。
傷病手当金
会社員や公務員などが加入する社会保険には「傷病手当金」を給付する制度があります。
病気や怪我のため、働けない日が連続して3日以上ある場合、4日目以降から1日につき、給与の3分の2が支給されるという制度があるので、覚えておきましょう。
最初に支給された日から最長1年6ヶ月まで支給されるので、もしも一時的に働けなくなり収入が減ってしまう場合でも、少し安心して生活することができます。
ただし、加入している健康保険が国民健康保険の場合には、傷病手当金は給付されません。
所得税の医療費控除について
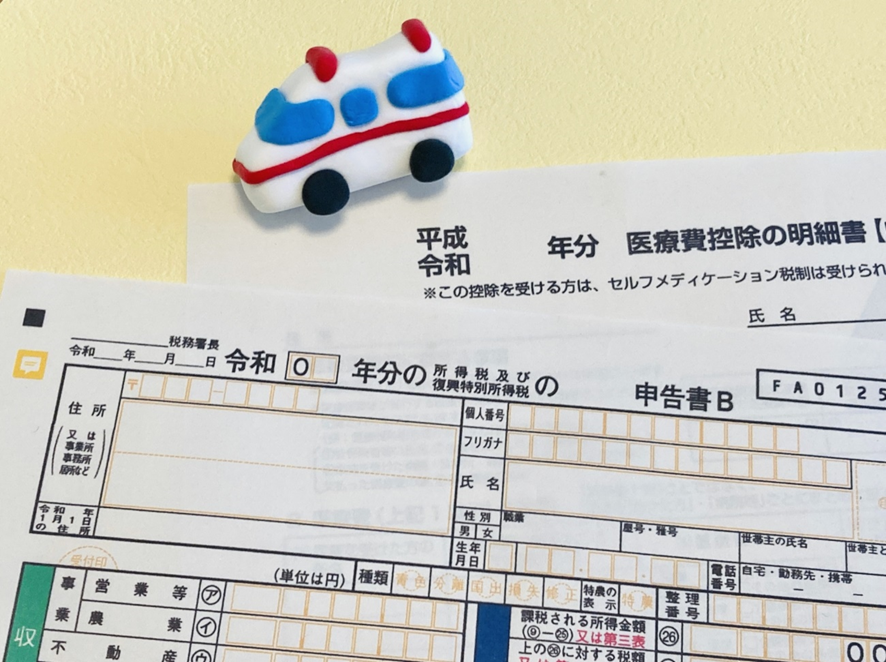
所得税の医療費控除は、がん治療を受ける期間が長引き、1年のうち、1月1日から12月31日までの1年間に定められた金額以上の医療費を自己負担した場合に、納めた金額の一部が還付される制度です。
実際に支払った医療費の合計から保険金などで補填される金額を差し引き、さらに10万円を引いた金額を医療費控除の対象とみなします。
ここで注意したいのは、所得が200万円未満の方の場合は、総所得金額などの5%を10万円の代わりに差し引きして医療費控除の対象額を計算する点です。
計算方法が変わるので、間違えのないよう注意しましょう。
利用できる公的医療保険を活用し負担を抑えましょう
がん治療は治療部位にもよりますが、治療が長期化する場合もあります。
その期間、働くことができず、高額な治療費がかかると、負担は大きくなりがちです。
窓口での支払いが数割負担になる公的医療保険を始め、高額医療費制度、所得税の医療費控除、利用すれば負担を抑えられる制度は幅広く用意されています。
また、加入している健康保険によっては傷病手当金を受け取ることもできるので、会社などへ確認し、活用することで、さらに負担を抑えて治療を行うことができるでしょう。
公的医療保険は普段あなたが納めている税金によって成り立つ制度です。
必要な場面で利用していきましょう。

